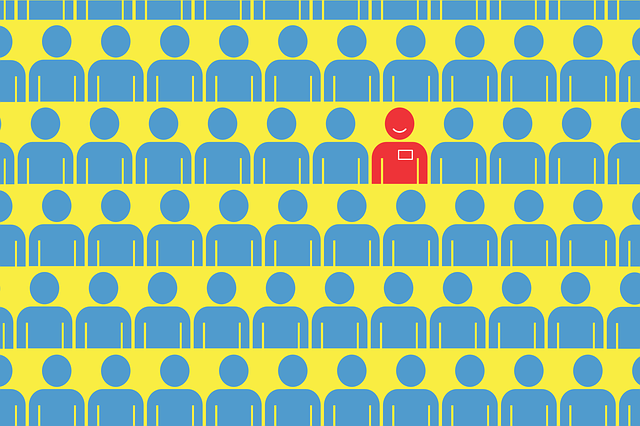
学校(日建学院)に通った筆者、独学の夫、結果的に宅建試験の勉強法がとても似ていました。私たちが受かった勉強法をみなさまにお届けします。これから勉強するみなさまのロードマップになりますように。
この記事で分かること
①試験日までの勉強の順番(5月ごろから始めた場合)
②勉強のコツ
③試験日当日にできること
独学で使った参考書やアプリはこちらを参考にしてみてください。
【宅建士受験者必見!】 学校に通うor独学 おすすめはどっち? | ナツ子のブログ
宅建士 試験勉強スケジュール

5月 権利関係
6月 宅建業法
7月 法令上の制限
8月 税その他、権利関係
9月 過去問を解く→間違えた問題の復習→必ず解けるようにする
10月 過去問を解く→間違えた問題の復習→必ず解けるようにする
- 5~8月はテキストを読んで、言葉に慣れる、内容を理解する
- 9月ごろからは過去問や予想模試やりまくるイメージ
5問免除講習は必ず受ける。お金で得点を買いましょう。
講習を受けることで、自分は絶対に合格するんだ!と気持ちを高めることができます。
権利関係
内容がとても難しいです。日常で使わない言い回しに、理解するまでにとても苦労します。勉強に時間がかかります。理解できるまで、最初に時間をたっぷり使ってください。9月までの時間や気持ちにゆとりがあるときに、じっくりたくさん問題を解いてください。短期詰め込みの勉強法では、全く得点は伸びません。
宅建業法、法令上の制限、税その他
内容が難しいというより、数値など細かい違いを問われます。早い時期に頑張って覚えても、実務で使わない限り、すぐに忘れます。言葉に慣れる、テキストの内容を理解する、サラッと勉強するイメージでいいと思います。
9月ごろから過去問や予想模試、を徹底的にやってください。
過去問を制したものが宅建試験を制する!
これはどの試験もそうかもしれませんが…
なぜ受かったのかを振り返って考えると、これに尽きます。
宅建士 試験内容
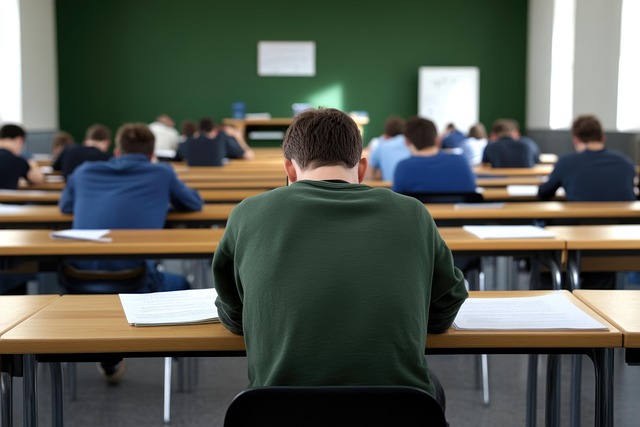
| ①権利関係 | 14問 |
| ②法令上の制限 | 8問 |
| ③税その他 | 3問 |
| ④宅建業法 | 20問 |
| ⑤5問免除科目 | 5問 |
| 合計 | 50問 |
合格ラインが毎年35点前後です。(毎年前後します)
例えば、法令上の制限が0点でも、他の科目で35点分あれば合格です。
得点が取れる科目で全力で勝負が合格のカギです。
「法令上の制限」「宅建業法」
9月からの追い込み期間は、この2科目を徹底的に暗記してください。
時間をかけた分だけ、得点が必ず伸びます。
10月ごろからは
権利関係は捨てましょう!!時間をかけても得点が伸びないからです。
試験当日の問題の解き方
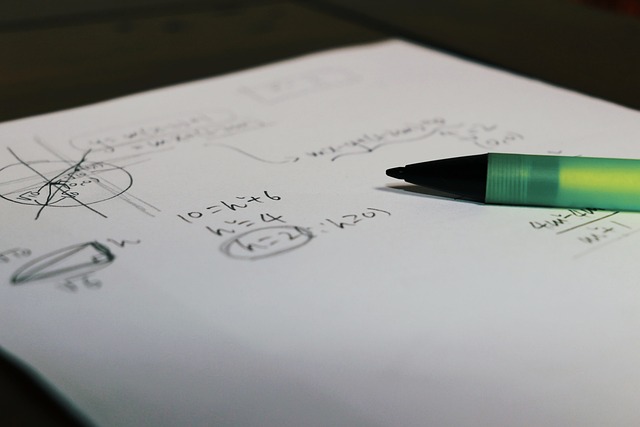
①宅建業法
②法令上の制限
③税その他
④権利関係
いろんなやり方があると思いますが…
私のおすすめはこの順番で解く方法です。
理由は
- 得点源になる科目を、一番集中しているときにできる
- ①②は最後の追い込みで暗記できているので、問題を解くのに時間がかからない
- スラスラ問題が解ける良いイメージを保ちながら、権利関係の問題に集中できる
- 権利関係でつまづくとメンタルが崩れる、時間も取られる
→得点源の宅建業法の問題を解くのに、とても焦る
これは、当たり前に皆さん実践されてるかもです(;’∀’)
しかし、夫は権利関係の問題を解くのが好きという理由で、試験日当日も権利関係から問題を解いていました。時間が無くなって焦って宅建業法の問題を解いた、終了時間ギリギリで問題全てを解き終えたそうです。
筆者は試験日当日、すべて回答後、全て問題の見直して、さらに時間に余裕があったのを今でも覚えています。
過去問を解くときに試してみてください!


コメント